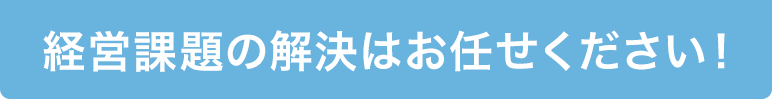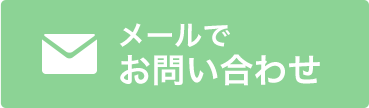※この物語は、TOMS田中会計グループにおける業務のモデルケースを想定して作成されたフィクションです。
【Section6】
“書類”で実態の把握に努め、“現場”で実態の把握を補う

【問題点 その1】
棚卸資産の計上漏れについて(未着車両)
さて、今回の棚卸資産(具体的には車両在庫)の計上漏れについて。簡潔に図説すると以下のようになります。
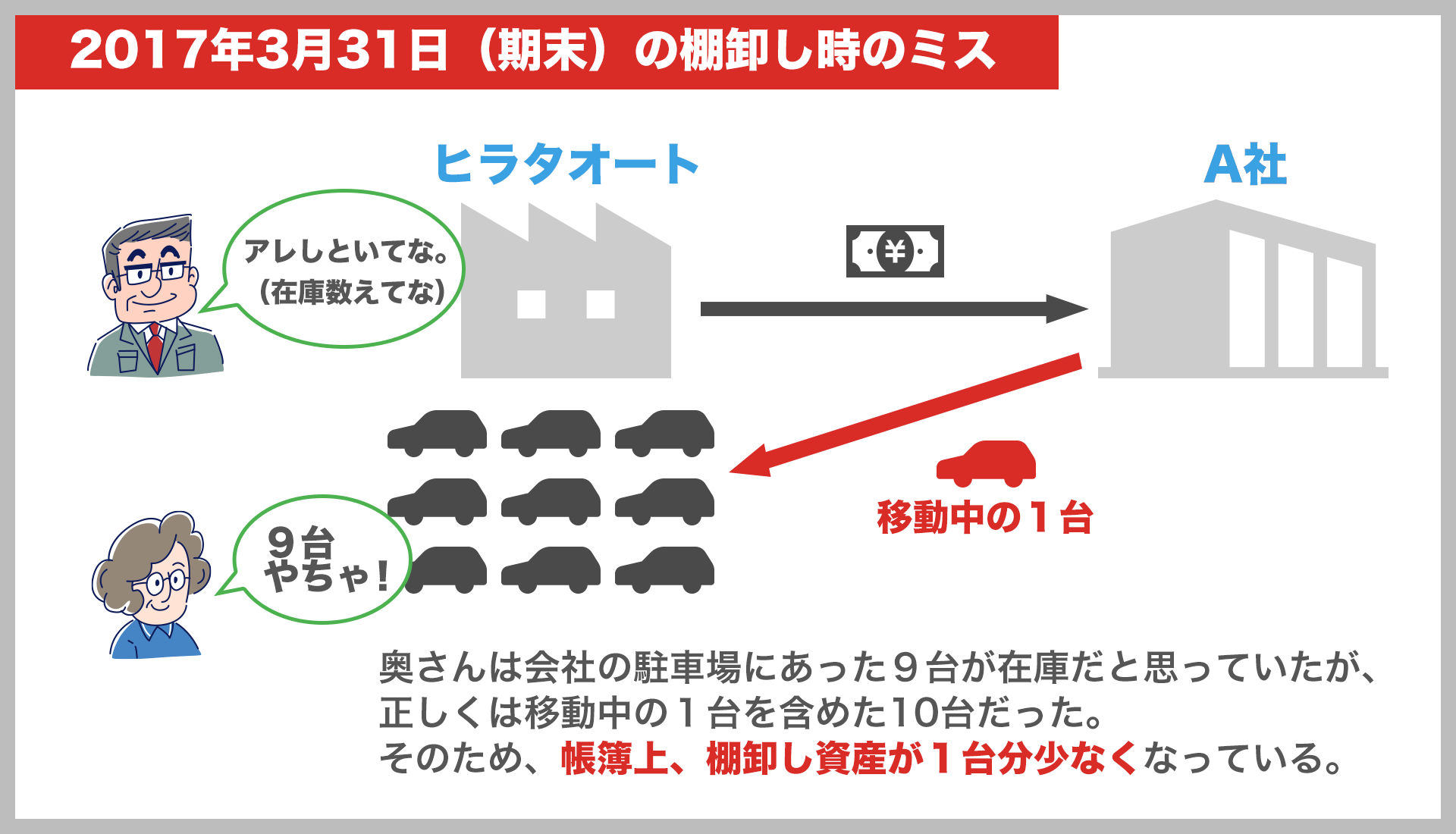
このように、奥さんは期末時点に駐車場にあった“現物”だけを数え、未着車両の計上を漏らしたまま棚卸表を完成させます。そうして4月に入ってから、先の車両の請求書を社長から受け取り、3月分の経理処理として、A社から請求された金額を未払金で計上。
本来であれば、それに合わせて期末の棚卸資産も“プラス1台”で計上し直す必要がありましたが、奥さんはそのことには気が付かず、計上漏れのある棚卸表に従って、1台少ない金額のまま計上してしまいました。
このように現場の事情を汲み取れば、今回のケースは“意図的な計上漏れ”ではなく、平田さんと奥さんの“コミュニケーション不足・行き違い(オペレーション上の不注意)”に主な原因を見出すことができそうです。

もう、ほんと、あんたは“アレアレ”ばっかりで、車が届いていないとか、そういうのをちゃんと詳しく言ってくれなきゃ、わかんないじゃない!

いや〜、そんな年がら年中、“アレアレ”言っとりゃせんだろう。でも、お前だって、はいはい言うて、ちゃきちゃき返事するから、こっちも通じとるもんだとばかり…。

思い込みによる行き違いというものは、常に起こりうるものですよ。請求書のように書面として、あるいは何らかのデータとして“目に見えるもの”があったならば、後日でも計上漏れに気付けたのかもしれません。
しかし今回のケースでは、目に見えるかたちで共有されるべきものが、おふたりの“頭の中(思い込みの中)”にしまわれ続けてしまいました。
【問題点 その2】
雑収入の計上漏れについて(スクラップの売却)
“雑収入の計上漏れ”も、税務調査の対象になりやすい項目です。金額の少なさが、つい油断を招くのでしょう。
御社では、自動車整備の際に発生したスクラップを、定期的に廃品回収の業者に売却していました。その一連の処理に関わる問題点です。
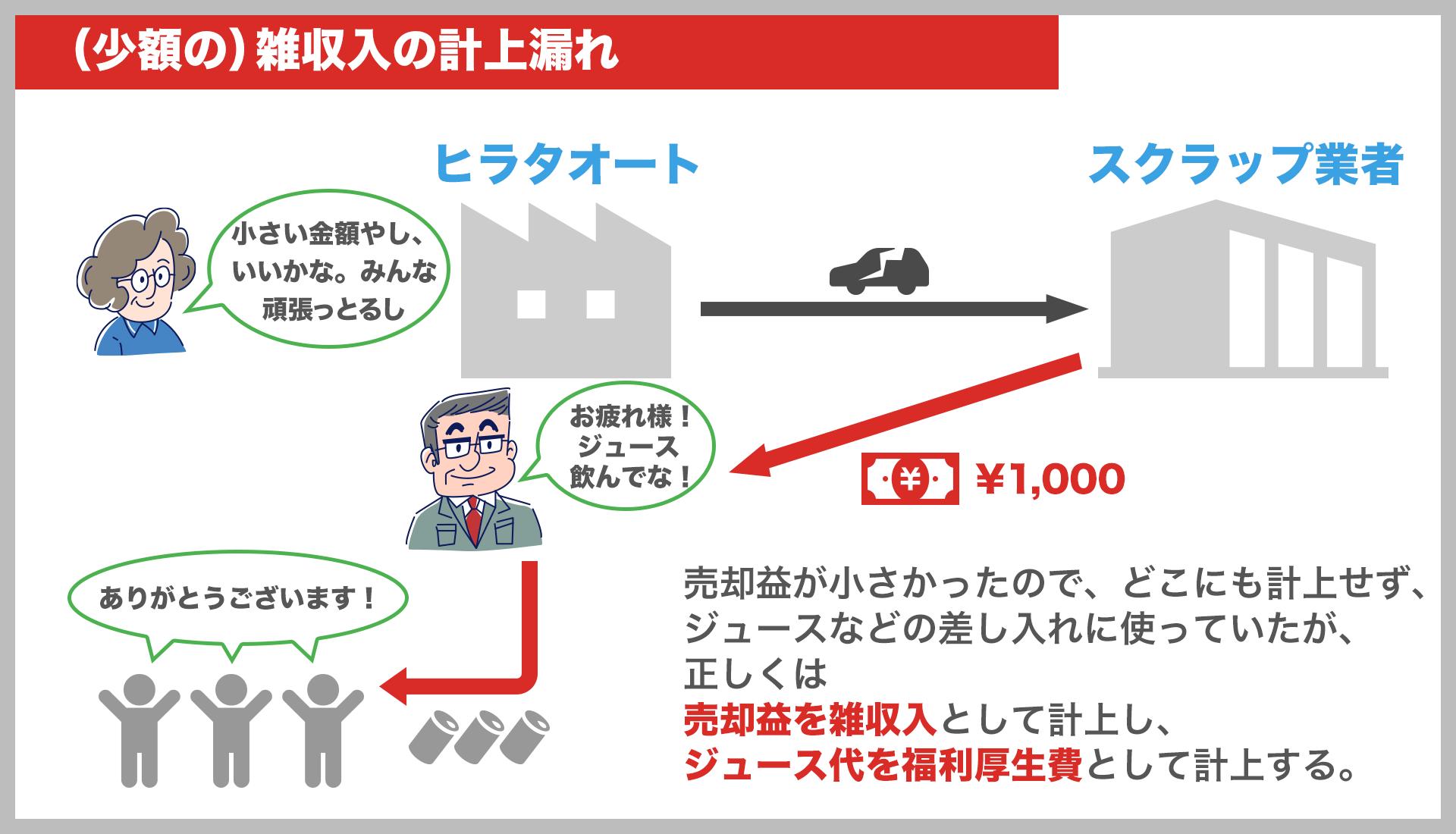
事前の調査でスクラップの売却が行われていることを知っていた税務署は、この雑収入の計上漏れにも気付き、しっかりと指摘してきたんですね。

ううん、社員たちが汗流しとるのを目にすると、どうも…。ぽんと入ったお金やし、そのまま、つい…。

先ほども実際に作業場にお邪魔しましたが、この季節でも随分と蒸し暑さを感じました。梅雨時や夏場の厳しい暑さは想像に難くありません。
冬は冬で冷たい外気にさらされることでしょう。暑さ・寒さに耐えながら一生懸命作業する従業員の姿を見て、飲み物代くらいはと思われる気持ちもよくわかります。

この人、妙に情に深いところがあるから。

従業員を思いやれるというのは、とても素晴らしいことだと思いますよ。
しかし、どんなに小さな取引・金額であっても、会社のお金に関わることである以上は、“適正な経理処理”を行わなければならないという、よい教訓ですね。
・
・
・


さて、今、お話した2つの計上漏れですが、お二方からすれば、決して意図したものではない、ということになりますよね。しかし、会計資料上、第三者が見た場合、もしかしたら、そうとは映らないかもしれません。
正直に企業活動を営んでいるつもりでも、しっかりと企業会計の原則に従って会計処理が行われていなければ、場合によっては「不正会計(意図的に行われた虚偽の会計)」と見なされることもありうる、ということです。

えっ!? そ、そんな…。でも、しっかりと会計処理しろって言われても…。
き、企業会計、ですか。ううん、頭いたなる。

でも、こうして税務署に、帳簿の中をアレコレ指摘されたりするとねえ…。
やっぱり、ちゃんとしないといけないのかしら…。

企業会計の慣行に従って帳簿をつけるのは、なにも税務調査のためだけではないんですよ。むしろ、自社の経営のためだと考えてみてください。
企業会計の原則に基づいて整えられた帳簿等の会計資料は、自社の財政状態や経営成績を経営者に把握させる、客観的で合理的な指針になります。いわば、「経営の羅針盤」です。羅針盤を持たずに、経営という大海原に漕ぎ出せるでしょうか?

はあ、たしかに…。
方角もわからなきゃ、外海に出る前に、寒ブリ漁の定置網に引っかかるのがオチですな。いや、なるほど、なるほど。
それから、田中は平田社長と奥さんの疑問や不安の声に耳を傾け、それに対して丁寧に受け答えしたのち、高橋を連れ立ってヒラタオートを後にした。
外に出ると、もうすっかり陽は傾いていた。引き伸ばされたように長く淡く伸びる影を眺めながら、高橋は自分の現場調査の甘さに我ながら肩を落とした。
昼間の暑気はすっかりと薄らいでおり、近くにある田んぼからは、カエルたちの鳴き声がケロロケロロと鳴り響いてきた。

事務所への道中、田中は車を路肩に停めるよう高橋に言った。
そして、すぐ近くにある自動販売機でお茶のペットボトルを2本買い、その1本を高橋に差し出して、ぽんと励ますように肩を叩いた。

これはポケットマネーから出したものだから、福利厚生じゃないよ。
そうして、田中は「わはは」と笑った。
比美乃江(ひみのえ)公園からは、この季節には珍しく、うっすらと、しかし確かに、悠然と連なる立山の姿が眺められた。
【Section7】
月次顧問契約、そして、巡回監査へ

およそ1ヶ月の時が流れ─、6月の中旬、TOMS田中会計グループ。
ヒラタオートの件では、税務署との折衝・調整も済んで、無事、修正申告が終わっていた。そのお礼にと、平田社長と奥さんが事務所を訪ねてきたのだ。
ふたりは、田中と高橋の前で、ほっと肩を撫で下ろし、さも解放されたといった具合に安堵の息を長々と吐いた。

いやあ、今回は助かりました。田中さんや高橋君には、本当によくしてもらって…。あの、これからも引き続き、わたしらの会社の面倒を見てはもらえんでしょうか?

もちろん、お引き受けさせていただきますよ。

ああ、よかった。ありがとうございます。よかったな、お前!

ほんとうにね、あんた! ああ、よかったわあ。これで安心。


こちらこそ、今後とも、おふたりとお付き合いさせていただけるというのは、本当に嬉しいことです。無事、税務調査も終えることができましたし、きっと肩の荷が下りたような心地がしていることだろうと思います。
しかし、これで安心と気を抜きすぎてしまってはいけませんよ。
この田中の言葉に、平田社長と奥さんだけでなく、高橋も反射的にぴっと背筋が伸びた。

平田さん、あなたはこの会社経営を通じて、叶えたい夢はありますか?
御社にも先代(創業者)が人生観や信念、哲学等を託して、力強く掲げた経営理念があることでしょう。そして、その経営理念を実現させるために、まだまだ、取り組むべきこと、改善すべきことが数多くあるはずです。例えば…、
【EXAMPLE】
経営理念を実現させるための改善事項の例

などなど。言い出したらキリがないのですが、やるべきことはゴマンとあります。
とはいえ、これらの各項目への対策を個々にバラバラと手をつけていけば、それでよいのかというと、そう単純な話ではないんです。さまざまな対策を、複合的に、時に応じて、バランス感覚よく講じていかなければなりません。
これをすれば正解、なんてことはないんです。
難しく聞こえるかもしれませんが、まずは、“企業会計原則に基づいた会計”を実現するしくみや体制を作り上げて、「経営の羅針盤」をしっかりと手にすることです。私たちも、巡回監査を通して全力で支援していきます。

ぜひぜひ、それは、本当に頼もしい!

巡回監査自体は、この高橋ともうひとり、合わせてふたりの税理士が主に担当させていただきますが、平田さんたちのことは、私も含めグループが一丸となってサポートしていきますので、これからも一緒に頑張っていきましょう。

ぼ、ぼくも精一杯、努めてまいります!
で、ですので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!
勢い込んだ高橋の大声は応接室にきんと響き渡ったが、その突飛だがどこか愛嬌のある彼のやる気は、平田社長と奥さん、そして、田中の頬をやわらかく緩ませた。

高橋君、ほんに頼りにしとるよ。

よろしくね!
梅雨入りの季節にも関わらず、からっと晴れた日差しが心地いい、穏やかな午後だった。
経営という大海原へ漕ぎ出したヒラタオートの航海も、高橋の税理士としての歩みも、まだ、はじめのひと漕ぎ、はじめの一歩。
そう、物語は、始まったばかりだ。
田中会計物語 、いかがでしたでしょうか?